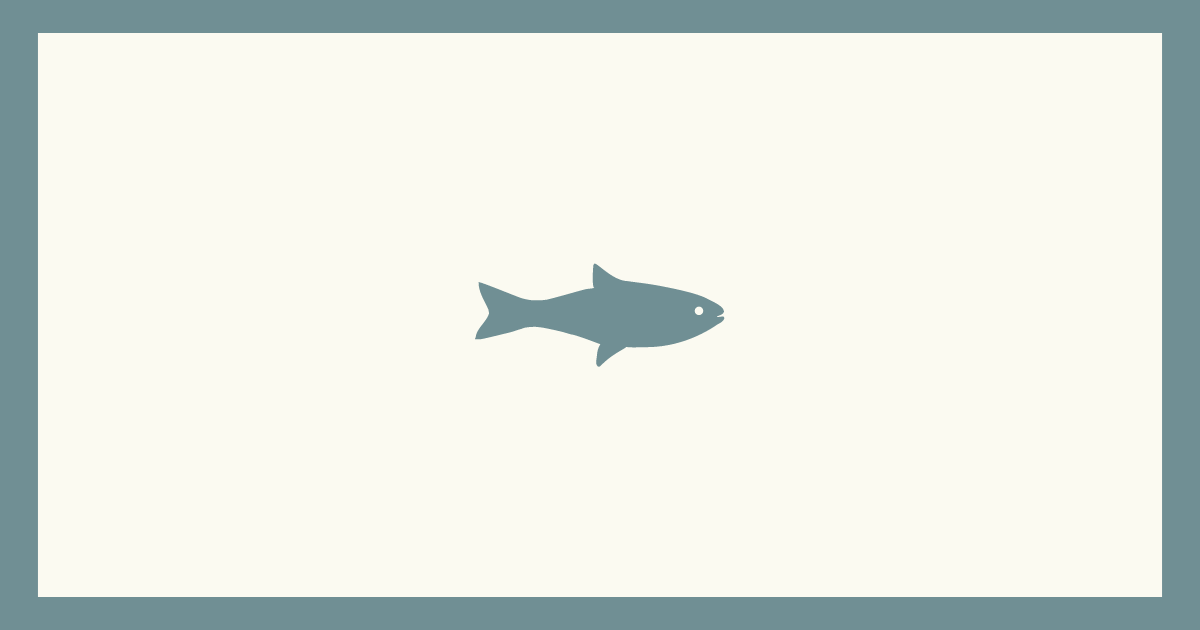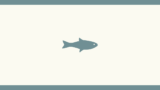舞台や演劇の現場では、一般的な左右の表現とは異なる独自の方向感覚が使われます。その代表的なものが「上手(かみて)」と「下手(しもて)」という言葉。
この記事では、これらの意味や使い方、由来について解説します。
「上手(かみて)」「下手(しもて)」の意味とは?
舞台における「上手(かみて)」と「下手(しもて)」は、演者から見た方向ではなく、客席(観客)から見た左右の位置を示す専門用語です。
- 上手(かみて):観客から見て右側
- 下手(しもて):観客から見て左側
たとえば、ある俳優が「上手から登場」と書かれている場合、それは客席から見て右側の舞台袖から登場するということになります。
なぜ「上手」「下手」と呼ぶのか? 〜その由来〜
「上手」「下手」という言葉の由来は、能楽や歌舞伎といった古典芸能にさかのぼります。
貴人の座る「上座」からの発想
日本の伝統では、身分の高い人や重要人物が座る場所を「上座」と呼びます。能や歌舞伎では、舞台右側(観客から見て右)が上座とされ、そこに格式高い人物や重要な役が登場することが多かったのです。これが「上手(かみて)」という名称の起源になったとされています。
逆に、舞台左側(観客から見て左)はそれに対する位置として「下手(しもて)」と呼ばれるようになりました。
現代の使い方と注意点
演劇だけでなく、コンサート、バレエ、オペラ、ミュージカル、テレビ収録などでも、「上手」「下手」は一般的に使用されています。
注意したいポイント:
- 演者目線と観客目線の違いに混乱しないこと。
- 舞台演出や照明の指示などでもこの用語が頻繁に使われるため、スタッフ間の共通認識として必須。
また、カメラワークや舞台図(プロット)などでは、「上手 → 右」「下手 → 左」という意識を徹底することが、正確な演出や演技に繋がります。
まとめ
「上手(かみて)」と「下手(しもて)」は、舞台芸術における方向を表す基本用語で、観客から見た右と左を示します。その由来は、日本の伝統芸能に根ざしたものであり、現代でもさまざまな舞台芸術の現場で重要な役割を果たしています。
舞台に関わるすべての人にとって、この用語の理解は基本中の基本。ぜひ覚えておきたい知識です。