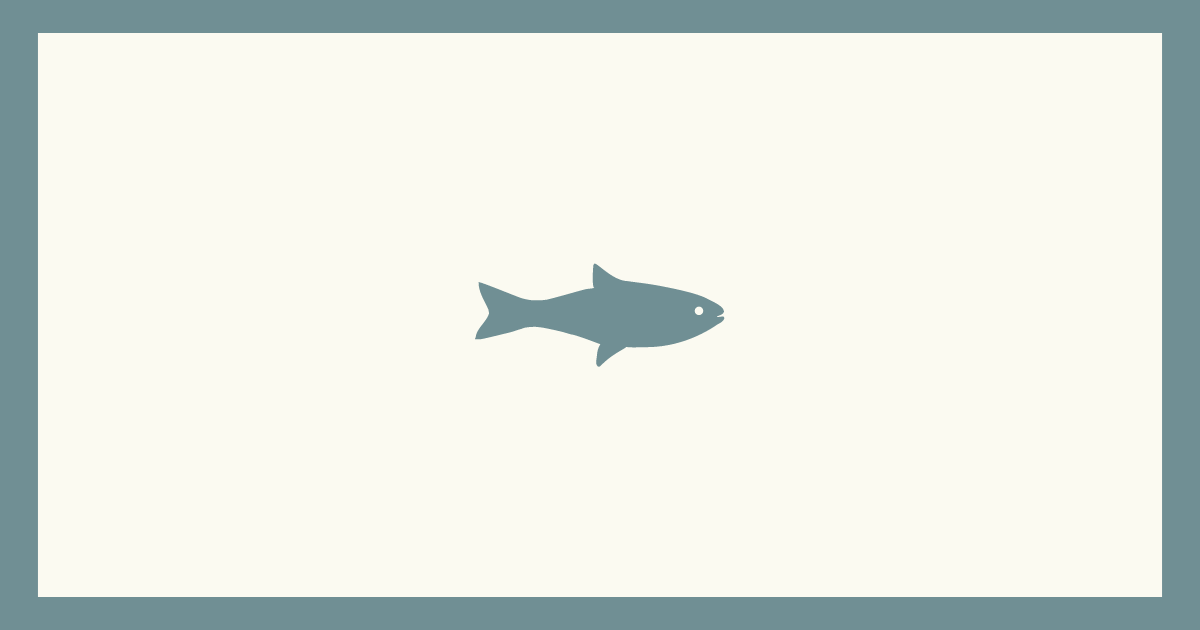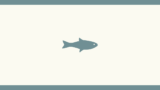吹奏楽やアンサンブルの練習で「周りの音をよく聴いて!」と指導されたことはありませんか?
しかし、実際には「どうやって聴けばいいのか分からない…」「聴こうとしても吹くことで精一杯…」という声もよく耳にします。この記事では、合奏力を劇的に向上させるための「周りの音を聴く」具体的な方法や思考法をご紹介します。
個人練習と合奏の決定的な違いとは?
個人練習は、自分の音の精度を高める大切な時間です。正しい音程、リズム、音色、発音など、基礎を固めることが目的となります。
一方、**合奏は“音楽の会話”**です。自分のパートを完璧に演奏するだけでは不十分で、周囲とどれだけ溶け込めるか、他のパートとどう関係を築けるかが求められます。合奏に必要なのは「耳」と「思いやり」なのです。
合奏で「聴く」べき3つのポイント
1. 基準となる音を見つける
「周りの音を聴く」といっても、全員の音を均等に聴こうとすると情報が多すぎて混乱します。まずは自分のパートにとって“基準”となる音を見つけましょう。
- メロディ担当なら、ハーモニーや伴奏の動き
- ハーモニー担当なら、主旋律の動き
- 同じフレーズを奏でる他パートの音
「今、誰が主役なのか?」を意識するだけで、聴き方は格段に変わります。
2. 縦のタイミング(アタック)を揃える
音を出す瞬間=アタックのズレは合奏全体の輪郭をぼやけさせます。指揮だけでなく、他パートのアタック音を耳で捉える習慣をつけましょう。特に打楽器のアタックは非常に参考になります。
3. 響きのバランスを探る
合奏は「音の混ざり」が命。自分の音が埋もれていないか、出すぎていないかを常にチェックしましょう。録音を聴いて、パートのバランスを客観的に聴くことも有効です。
思考法:聴くことは“受け身”ではなく“積極的な行動”
「聴く」という行為を受け身に捉えがちですが、合奏における聴く力は能動的・戦略的な行動です。
- 「今、どのパートと合わせるべきか?」
- 「誰の音を参考にすべきか?」
- 「このフレーズは支える側か、引っ張る側か?」
こうした問いを頭の中で回しながら演奏することで、音楽に立体感が生まれ、アンサンブルが一気に成熟します。
アイコンタクトの重要性:視覚からも“音”を感じる
視線や身体の動きは、音以上にタイミングを合わせる手助けになります。
特に次のような場面ではアイコンタクトが非常に有効です。
- フレーズの入りや切り替わり
- rit.(リット)やaccel.(アッチェレランド)などのテンポ変化
- ソリや対話形式のフレーズ
指揮者を見ることに加え、隣のパート・連携する楽器と視線を交わすことで、合奏の精度が一気に高まります。
実践!練習で取り入れたい「耳トレ」方法
- パート全体でハーモニーを出してみる → チューニング音だけでなく、和音を全員で出してみましょう。どの音が濁っているか、溶け込んでいるかを耳で感じ取る訓練になります。
- 録音を聴いて“聴きどころ”を探す → 合奏練習の録音を振り返り、「今、どのパートの音を聴くべきだったか」を分析してみましょう。
- 役割交換アンサンブル → 本来のパートとは違うパートを仮想的に演奏してみる(頭の中で)。そうすることで、「他のパートがどう聴こえているか」が理解できます。
まとめ:聴くことから、音楽は変わる
「合奏 音を聴く コツ」は、単なる技術ではなくアンサンブルへの意識の持ち方です。
周囲の音を積極的に聴き、関係を築くことは、演奏そのものを豊かにし、吹奏楽の醍醐味を最大限に味わえる瞬間をもたらしてくれます。
日々の合奏練習の中で、少しずつ“聴く耳”を育てていきましょう。合奏は、一人では決して味わえない音楽の魔法です。