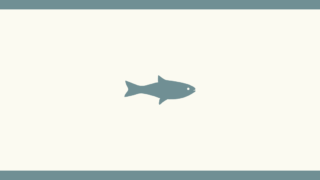 楽曲解説
楽曲解説 ワーグナーの愛と救済のドラマ《タンホイザー(Tannhäuser)》世俗と神聖の狭間で揺れる魂
リヒャルト・ワーグナー作曲のオペラ《タンホイザー(Tannhäuser)》は、愛、欲望、贖罪、そして救済という永遠のテーマを壮大な音楽とともに描いた作品です。全3幕からなるこの作品は、ドイツの伝説と中世騎士道文化を背景に、人間の内面的葛藤と...
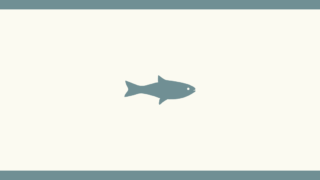 楽曲解説
楽曲解説 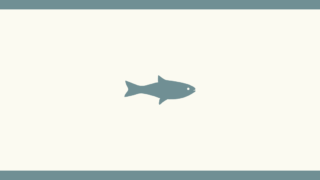 楽曲解説
楽曲解説 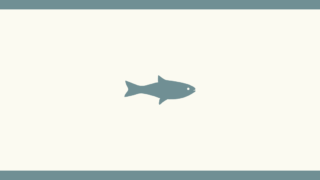 楽曲解説
楽曲解説 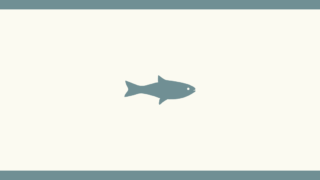 楽曲解説
楽曲解説 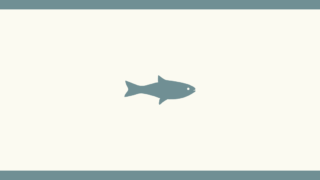 楽曲解説
楽曲解説 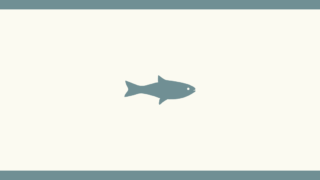 楽曲解説
楽曲解説 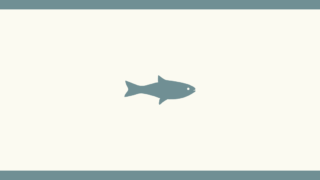 楽曲解説
楽曲解説 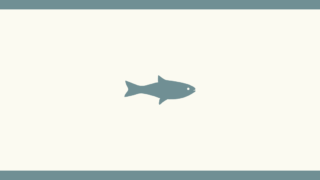 楽曲解説
楽曲解説 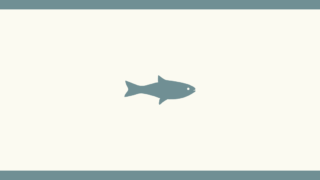 その他
その他 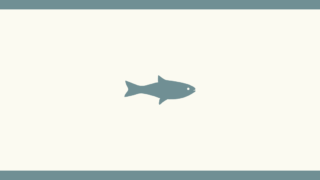 その他
その他 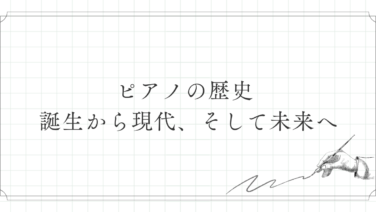 楽器学
楽器学  楽曲解説
楽曲解説